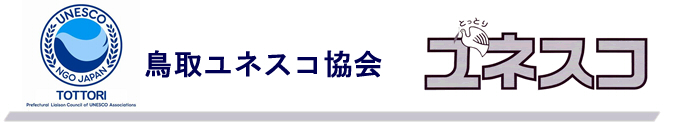
�g�b�v�y�[�W
���惆�l�X�R����Ƃ�
���������
���m�点
���惆�l�X�R����̂����
����Ȋ������Ă��܂�
���{���l�X�R����A��
���C��i�k�b��j
�u����
���ǂ��p�ꋳ��
�G�莆����
���ی�
�G��W
�����̗�
�`�����e�B�[�o�U�[
�R�[�A�N�V����
���捻�u��Đ��|
���̔��s
�r�b�O�j���[�X
��������Ɋ������܂���
������̂��ē�
�������
������A�^������A�@�l���
���ʖ@�l���
|
���C��i�k�b��j��8��u���v�k�b��
2014�N9��13��(�y) 13�F30�`14�F45 �w���g���Ő��E�̎R�x�X�͂͏��łɌ��������H�\���A�������A�ό��ւ̊�@�\�x �u�@ �t�F ���� ���� ��(NPO�@�l �X�́E��X���������� ��\) �� �@���F�@ ������ف@��P��c��
�T�v�F ���E�̎R�x�n��̕X�͂̓��A�X�J���W�i�r�A��j���[�W�[�����h���̈ꕔ�̒n��ł�1980-90�N���ɑO�i(�g��)�̌X�������������A1990�N�ȍ~�͑S�Ă̒n��̕X�͂����(�k��)������B �@�R�x�X�͂���т��̎��ӂ̐ϐ�́A 1) ������(�@ �����A�_�ƁA�H�Ɨp���A�A ���͔��d) 2) �ό�(���N���G�[�V�����A�X�|�[�c���܂�) �Ƃ��đ傫�Ȗ������ʂ����Ă���B�X�͂���ނ܂��͏��ł���ƁA�ꕔ�̍���n��ɂ͑傫�ȑŌ��ƂȂ�B�Ƃ��ɁA������������n��ł͐��Q�[�A�Ђ��Ă͐[���ȐH�Ɠ���O�����B �@�����I���A�X�͏�̍~��ʂ̑����^�����ɂ��傫�ȉe�����邪�A�����~��ʂ��ς��Ȃ��Ɖ��肵���ꍇ�A�N���ϋC�����R���㏸����ƁA�X�͂̒��S���x(�������́A���t�����x�܂��͐��)����500m�㏸����ƍl������B��������ƁA�Ⴂ�R�܂��͏��K�͂ȕX�͂͏��ł��邪�A���R��Ɋ��n��̕X�͂͑�����������B�������A��������ό������Ƃ��ẮA�n��ɂ���Ă͉�œI�ȏƂȂ邾�낤�B ![�p�^�S�j�A�A�y���[�g�����m�X�̖͂��[�Ɗό��W�]��](img/20150514_sec04_03.jpg)
�p�^�S�j�A�A�y���[�g�����m�X�̖͂��[�Ɗό��W�]�� ��7��u���v�k�b��
2014�N4��26��(�y) 13�F30�`14�F45 �w����s�X�n�ɏo�v����쐶�����\ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C�m�V�V�E�j�z���W�J�E�c�L�m���O�}�|�x �u�@ �t�F�@ ���@�@�M ��@��(���挧�������� �ΖL���Ȏ��R�� �W��) �� �@���F�@ ������ف@��P��c��  �m�v �|�n
�m�v �|�n�@�ߔN�A�j�z���W�J��C�m�V�V�ɂ��_�Ɣ�Q��X�є�Q���S���Ŗ��ƂȂ��Ă��܂��B���挧�ł�30�N�O�́A�C�m�V�V�͐����Ȃ��A�j�z���W�J�͂܂�ŁA�c�L�m���O�}�͐�ł��뜜����Ă��܂����B���������݂ł͒���s�̎s�X�n�߂��܂ŃC�m�V�V�A�j�z���W�J���i�o���A�v���R�ł��c�L�m���O�}�̖ڌ���������悤�ɂȂ�܂����B ���ɂ��^�k�L�A�A�i�O�}�A�e���A�O����̃k�[�g���A��A���C�O�}�܂Ői�o���Ă��Ă��܂��B����s�𒆐S�ɁA�ߔN�̕��z���Љ�A�Ȃ����������ɂȂ��Ă����̂��F����Ƌ��ɍl�������Ǝv���܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(���@�M��) �m��ÎҎG���n �@���挧�ł́A�c�L�m���O�}�A�C�m�V�V�A�j�z���W�J���ꂼ��́u�ی�Ǘ��v��v���߂Ă���B���̒��ŁA�c�L�m���O�}�̊Ǘ��ڕW�Ƃ��Ắu�Z���̈��S�ƈ��S�̊m�ۂ�}��Ȃ���A�N�}�̐��������̈���ƒn��̌Q�̈ێ���}��v�Ƃ������Ă���B����A�C�m�V�V�ƃj�z���W�J�̊Ǘ��ڕW�́A�N�}�Ǝ��Ă͂��邪�u�̐������ɂ��l�Ԋ����Ƃ��a瀂̌y����}��v�Ƃ��ϋɓI�Ɂu�������v��ł��o���Ă���B �@��7��w���x�k�b��ł́A���̂悤�Ȗ쐶�����́u�Ǘ��v��S���Ă��钹�挧���������ΖL���Ȏ��R�ۂ̐��Ƃ���b�����Ƃɂ����B�^�C�g�����u����s�X�n�ɏo�v����E�E�E�E�v�Ƃ������A�K�������X���Ƃ��Z��n�݂̂�z�肵���킯�ł͂Ȃ��B�P�Ɂu����s�v���ƁA��m�R�̒���܂Ŋ܂�ł��܂��̂ŁA�����ł̎s�X�n�Ƃ́A�l�X����炷�������Ƃ��̎��Ӓn��A�Ƃ����Ӗ��Ƃ����B �@�܂��A�T�u�^�C�g���ɂR��ނ̑�^�������f�������A����͕��I�A�l�I��Q���傫���Ǝv����쐶�������ے��I�Ɏ��������̂ł���B���ۂ́A����s���̏Z��n�̒�ȂǂɁA���ɑ����̎�ނ̓������o�v���Ă��邱�Ƃ�����̍u���Œm�����i�ʐ^�Q�Ɓj�B�댯��`���Đl�̋��Z�n��K���̂́A���������ɔ��������������邩��ɈႢ�Ȃ��B �@��ʎQ���҂̈�l���A�{�i2014�j�N2��15���A�v���R����{�w�R�ւ̏c�����Ă������A�Ζʂ��삯���N�}��ڌ������B�~�����Ă���͂��̎����Ȃ̂ɉ��̂��Ǝv���B�����ɂ��ƁA�u��{�I�ɓ~�����邪�A�ꎞ�I�ɖڊo�߂Ċ�������Ƃ��A�a���\�������ē~������K�v���Ȃ��Ƃ��A�Ⴍ�ē~�����w�K���Ă��Ȃ��͓̂~�����Ȃ��ꍇ������v�Ƃ̂��Ƃł������B  �@���ꂩ�玄�������쐶�����Ƃǂ��ւ��A�Ώ�������悢���A�s����s�������͂��ĉ������ׂ������̉ۑ肪�����яオ���ƂȂ����B
�@���ꂩ�玄�������쐶�����Ƃǂ��ւ��A�Ώ�������悢���A�s����s�������͂��ĉ������ׂ������̉ۑ肪�����яオ���ƂȂ����B(�����裒S���F��������) �A���C�O�}�i����s�������A2013�N3���A��̒r�̌��_���ďo�v�����Ƃ���F�Z���j ��U��u���v�k�b��
2013�N9��28�� (�y) ��A�т����͂ǂ��Ȃ邩�H�|�M�сA�����n�A���{���Ƃ��ā[� �b��ҁF���� ���I�q�� (��B��w�_�w�� �w�p������)  �m�T�v�n
�m�T�v�n����������l�X�̐�������邽�߁A������̂����t�����H���Ĕ��邽�߁A�����̂��̂���Ƃ�Ƌ���������A�d�Y�ނƂ��Ďg�����߁B�l�X�ȗ��R�̂��߂ɁA���E�e�n�ŐA�т��s���Ă���B���̂悤�Ȑl�H�т͌��ݐ��E�̐X�іʐς̂���7�����߂Ă���A�X�ѕی������ւ̊S�̍��܂肩�獡��A��������Ɨ\�z�����B �@���Ƃ��Ί����n�ł̐A�т́A�⋭���h�~�̂��߂ɖ�A����B���̂��߁A���ɖ�����Ă��A��芲�点�����������ł�����������p�����Ă���B����ŁA����A�W�A�ł́A�S����[�J���A�A�J�V�A�Ƃ������O������ɂ��l�H�т��������Ă���B�����͐������������ƓI���l���������ʁA�����g��������Ƃ������O��������Ă���B �@���ۂɁA�J���{�W�A�ŏ��U�ʂׂĂ݂�ƁA�J���~��Ȃ������ɊO������̃��[�J���̏��U�ʂ��V�R�����荂���Ȃ�X�����������B �@���{�ł́A�؍މ��i�̒ቺ��l������Ȃǂ̗��R�������ꂪ�s���͂��Ȃ��X���������Ă���B���̂悤�ȊǗ������l�H�т�����ǂ�����ׂ����ɂ��āA�؍ދ��������łȂ��������̈���I�ȋ�����ЊQ�̖h�~�Ƃ����ϓ_����l����ƁA�Ԕ������ėѓ��𖾂邭���A���w�A���𑝂₷���Ƃ��ЂƂ̉������@�ɂȂ肤��B �@���̂悤�ɁA����ɐA�тƂ����Ă��A�ꏊ��K�́E����ɂ���Ė��_���ς��B���̎����͒����A�A�т���Ƃ��ɂ͗\�z���Ȃ�������肪�łĂ��邱�Ƃ�����B  �@����́A���������ǂ̂悤�Ɏg���̂��A�ɒ��ڂ�����������ނɘb�������Ă����������B �@����́A���������ǂ̂悤�Ɏg���̂��A�ɒ��ڂ�����������ނɘb�������Ă����������B�@���ꂩ��́A�A�ь�A�����I�ɊǗ����K�v�ɂȂ邩�炱���A���̐X�𗘗p���A�����Ő�������l�����̕�炵���l���Ă��������Ǝv���B �m�ʐ^�n�J���{�W�A�̃S���l�H�сi2009�N�A���ΎB�e) ��T��u���v�k�b��
2013�N3��23��(�y) ��k�ɂ̕X�������Ă���I ���{�̋C�ۂւ̉e���́H� �b��ҁF���� ���� NPO�@�l �X�́E��X���������ɑ�\�A����ɉz�~����
�m�T�v�n�@
�@�k�ɊC�ɕ����ԕX��2012�N�̉Ă͒������Z���A�X�����{�̊C�X�ʐς͊ϑ��j��ŏ��ƂȂ�A5�N�O��9���̖ʐς�����{������������Ȃ����B�O���[�������h�X���ł��A����i�W��3,216 m�j�t�߂�7���ɋC�����v���X�ɂȂ�A�L�͈͂ɕ\�ʂ̐Ⴊ�Z�����B�O���[�������h�̗Z��́A�ُ�C�ۂ�“�ҏ�”�ɂ����̂ŒZ���I�Ȍ��ۂɂƂǂ܂�̂��A���邢�͂��ꂩ�疈�ċN���钷���I�C��ω��̈ꑤ�ʂȂ̂����ڂ������ł���B �@����A�k�ɊC�ł͍L���̈�œ��˂̑唼�˂���C�X���Z������A���˂��z�����₷���C���ʂɕς�����̂ŁA�M�̃o�����X������A���{���܂ޖk�����̋C�ۂ�C��ɂ���ڂ��e���͔��ɑ傫���ƍl������B���N�A�܂��͂��̎��̔N�̓~�̊����A��̗ʁA�~�J�A�Ă̏����A�䕗�A���J�A�����Ȃǂ��ǂ̂悤�ȏɂȂ邩�͒N���\���͂ł��Ȃ����A �l�X�Ȗʂ�“�ٕ�”���������邱�Ƃ��\�z�����B  [�ʐ^]�k�ɊC�D��O�̔Z���F�͊C���ʁA�����̔����̈�͊C�����������C�X�A���i�̓O���[�������h�X��(2007�N7���A�{�R�G�����B�e) ��S��u���v�k�b��
�u�����v�S���F��������
2012�N9��20��(��) �v�|
�@�ꌩ����ƁA�������Ȃ����̂悤�ɂ�������A�n�ʂ̉��B �@�����������ɂ́A���ɑ��l�ȁu�y�듮���v�̐��E������܂��B
�y�듮�������i�~�~�Y��_���S���V�A���X�f�Ȃǁj�́A�����t�⓮���̎��́A���ȂǁA����Ύ��R�E�́g�S�~�h��H�ׂĕ������A�A�������̗{���ւƍĐ����Ă��܂��B
�T�v
�@�y�̒��ɂǂ�ȓ�������炵�Ă���̂��A����������ƌ���ꂽ��A�A���A�~�~�Y�A���O�����x�������B�������A���ۂɂ͐X�сA�G�ؗсA���A�뉀�A�Ƃ̏����ȂǁA������ꏊ�ɁA���ɑ����̎�Ɛ��̓y�듮�����������Ă��邱�Ƃ�m�����B�����̓y�듮���ɑ�^�A���^�A���^�܂ł��܂��܂���A���݂��Ɂu�H���v�u�H����v�Ƃ������G�ȊW���`�����Ă���B
�y�듮���Ƃ́A�n���ȑ��݂����A�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��������ł���Ƃ������Ƃ��ǂ����������B
��R��u���v�k�b�� �u�����v�S���F��������
2012�N3��17���i�y�j �T�v
�@ �@���挧�ł́A2010/11�N��2011/12�N�̓�~�G�����đ�Ⴞ�����B�Ƃ��ɁA2010�N��A�����痂�����ɂ����Ē��挧�����ɑ��ʂ̐Ⴊ�~��A2011�N1��1���̕Ďq�s�̐ϐ�[89�Z���`���[�g���́A1961�N�ȗ��ϑ��j��ō��ł������B�܂��A2011/12�N�~�G�Ԃ̖����̍~��[�����v�����ʂ́A����s��3.39���[�g���ɂ���сA�i���a�j59����i1983/84�N�j�ȗ��̑��ƂȂ����B
�@����A�R�n�̐ϐ�͓V�R�̒����r�̖������ʂ����ƂƂ��ɁA�~��͑�C���A���X�͖�R��͐�ɓ�������A�ϐ�͑������z�����A��n�̓�����h���D�ꂽ�f�M�V�[�g�ł�����B���̂悤�ɁA��͎��R�������炰�A�������̕�炵��L���ɂ��Ă���̂ł���B �@���b�Ƃ��āA��ɉz�~���̊ϑ��A��ƁA�����Ȃǂɂ��ăX���C�h�ɂ��Љ���B ��Q��u���v�k�b��
2011�N10��22��(�y) ![�o�C�I�}�X�G�l���M�[���p�̓W�]](../img/20120123_013.jpg)
�T�v
�@ ��k�Ђƌ������̂Ɍ�����ꂽ�䂪���ł́A�����o�C�I�}�X�����̃G�l���M�[���Ƃ��Ă̗��p���}���サ�A���ڂ���Ă����B�o�C�I�}�X�����Ƃ��Ă͔_�ѐ��Y�n�̔_�ƊW�i�m�A���k�Ȃǁj�A�{�Y�W�i�ƒ{���A�Ȃǁj�A�ыƊW�i�Ԕ��ށA�}�t�Ȃǁj�A�p�����n�̗юY�E���Y���H�p�����A�����p�����i�����݁A�p�H���Ȃǁj�A�͔|�앨�n�̑哤�A�Ƃ����낱���A��ނȂǂƑ��l����ɂ킽���đ��݂��Ă���B�����̎����̃G�l���M�[���Ƃ��Ă̕ϊ��Z�p�Ƃ��āu�M���w�I�ϊ��v�Ɓu�������w�I�ϊ��v������B�����āA�ϊ������G�l���M�[�́u�o�C�I�}�X���d�p�v�A�g�[�p�⓮�͗p�́u�o�C�I�}�X�R���v�A�K�X�������u�o�C�I�K�X�v�ȂǂƂ��ė��p�����B �@�o�C�I�}�X���d�ւ̗��p�Ƃ��Ė؎��o�C�I�}�X���d�Ŗ����H�Ɓi���R���^��s�j�ł͎��Ђ̓d�͂����ׂĘd���A����ɔ��d�����Ă���B���̂ق��؎��o�C�I�}�X�Y�����d�A�o�C�I�}�X�K�X�����d�Ȃǂ��s���Ă���B�܂��A�؎��y���b�g��p������g�[�Ȃǂ����p�ݔ��̏[���ɂ���ĕ��y������B����ɁA�ŋߐA���S�~���g�������d�����݂��Ă���B �@���͗p�̃o�C�I�R���Ƃ��ĂƂ����낱���A�m�A�|�A�o�K�X�Ȃǂ���o�C�I�G�^�m�[�������ė��p������@�����p���������B�܂��A�ŐV�̋Z�p����g�����o�C�I�G�^�m�[���̌����I�Ȑ������@���A���ƃv���W�F�N�g�Ƃ��Č�������A���p������悤�Ƃ��Ă���B �@�����ɏЉ����̓o�C�I�}�X�G�l���M�[���p�̂����ꕔ�ɂ����Ȃ����A���コ��ɑ����ʂɂ킽���ăo�C�I�}�X�̃G�l���M�[���p���g�債�čs���ł��낤�B�܂��A�����Ȃ邱�Ƃ����҂���Ă���B ��1��u���v�k�b��
2011�N6��21��(��) �@���惆�l�X�R�����Â̑�P��u���v�k�b��i��ʌ��J�j���A2011�N6��21���i�j16�F00�`17�F20�A���悳����قɂĊJ�Â��ꂽ�B���̒k�b��́A�L�`�̊����̒��ŁA���̎��X�̎Љ�I�S�̍����e�[�}��I�сA�b��҂̍u���̌�A���l�X�R���������ш�ʎQ���҂��b�������A���ӎ������߁A���l�X�R����̊����Ɏ����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B
�@ ��P��ڂ́A�k�b��ݗ���Ď҂̐����������ɂ��A�w�Đ��\�G�l���M�[��d�͂̎���ɂ��邽�߂Ɂx�Ƒ肵�Ęb����s��ꂽ�B���̍��q�͈ȉ��̒ʂ�ł���B  *�p�����̏����͔��d���i�ʕ{�d���_�Ƌ����g���j �ő�o��117 kW�D  *�k�h���̕��͔��d�@�D �P����蔭�d�ݔ��e��1,500 kW�D �@�n�����g���h�~�̂��߂ɂ͉��ΔR���̏�����팸���邱�Ƃ��̗v�����A���������Ζ��A�ΒY�A�V�R�K�X���͉����Ȃ������A�͊��Ɍ��������Ƃ͊m���ł���B����g�N���[���ȃG�l���M�["�Ƃ̕W�ԂŊg�呝�݂��}���Ă������q�͔��d�́A���̈��S�ʂŖ������Ȑ[���Ȗ�肪�������݂��邱�Ƃ��I�悵���B���������Ă��ꂩ��́A���z���A���́A�������́A�n�M�A�o�C�I�}�X���A�₦����[����鎩�R�̃v���Z�X�R���̃G�l���M�[�A���Ȃ킿�Đ��\�G�l���M�[�i���R�G�l���M�[�j���d�͂̎���ɂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���[���b�p����{�̌�����T�ς��A�߂������̔���I�ȗ��p�g��̉\�����l�������B �i�u�����v�S���F��������j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����E�������ƈψ���S�����C��i���j�� �u�Q�O�O�U�N�X���Q�S���i���j�ɁA�ȉ��̍u����惆�l�X�R�����ÂŎ��{���܂����v
��O�Y �����Č��t�ɂ���Ȃ�A���̉̂����̎��̋C�����ł��B
�v���t�B�[�� 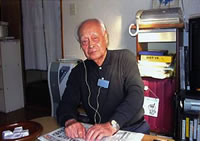 �͂���E�₳�Ԃ낤 �F �吳�V�N���ꌧ���܂�B���a�P�U�N�ɉƑ��ƒ��N�����ɓn�藤�R���퐻�����������Ƃ��ď]���B�I��̗��N�A�g�Ɋo���̖����X�p�C�e�^�Ń\�A�ɘA�s����A�V�N�ԃV�x���A�ł̋����J������������B�Y�����I��������A���͋����ꂸ�A�������Ď��̂��ƂłT�O�N�Ԍ��n�Ő����B���̊ԁA���n�Ń��V�A�l�̃N���E�f�B�A �E ���I�j�[�h�u�i����ƌ����B�\�A�����̕����W�N�ɓ��{�̉Ƒ��̖����������A���N�A�������B���̈ꐶ��Z�߂��{�Ɂu�N���E�f�B�A�A��Ղ̈��v�i�������q���j�Ȃǂ�����B �͂���E�₳�Ԃ낤 �F �吳�V�N���ꌧ���܂�B���a�P�U�N�ɉƑ��ƒ��N�����ɓn�藤�R���퐻�����������Ƃ��ď]���B�I��̗��N�A�g�Ɋo���̖����X�p�C�e�^�Ń\�A�ɘA�s����A�V�N�ԃV�x���A�ł̋����J������������B�Y�����I��������A���͋����ꂸ�A�������Ď��̂��ƂłT�O�N�Ԍ��n�Ő����B���̊ԁA���n�Ń��V�A�l�̃N���E�f�B�A �E ���I�j�[�h�u�i����ƌ����B�\�A�����̕����W�N�ɓ��{�̉Ƒ��̖����������A���N�A�������B���̈ꐶ��Z�߂��{�Ɂu�N���E�f�B�A�A��Ղ̈��v�i�������q���j�Ȃǂ�����B �@ �Ȋw�E���ێ��ƈψ���S�����C��i���j�� �u���{���l�X�R���[�X�X�^�f�B�c�A�[�����C���h�v�Q��������܂���
���E��ς���u�����v �\ �C���h �E �����̌��ꂩ��
|
���惆�l�X�R����
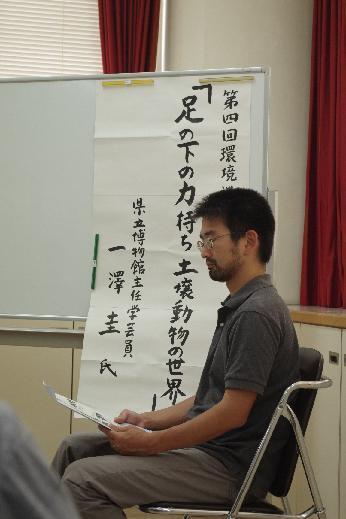





 �@�u�t�̐Ԗ؈�������́A���l�X�R�N�𗬊���ɂ��C���h�ւ̃c�A�[�ŁA�e�n���l�X�R����̐��E�����T�W���̉���҂���I�l���ꂽ�Q�O���̂����̈�l�ł��B�R���Q�U������P�S���ԂƁA���O���C�i���w�K�̃��|�[�g�A�c�A�[���̕��̍쐬�Ȃǁj�A���㌤�C�i���ꂩ��̃��l�X�R�����Ɍ������f�B�X�J�V�����Ȃǁj������܂����B���ݒ��揤�ƍ��Z�̋��@�ł��B
�@�u�t�̐Ԗ؈�������́A���l�X�R�N�𗬊���ɂ��C���h�ւ̃c�A�[�ŁA�e�n���l�X�R����̐��E�����T�W���̉���҂���I�l���ꂽ�Q�O���̂����̈�l�ł��B�R���Q�U������P�S���ԂƁA���O���C�i���w�K�̃��|�[�g�A�c�A�[���̕��̍쐬�Ȃǁj�A���㌤�C�i���ꂩ��̃��l�X�R�����Ɍ������f�B�X�J�V�����Ȃǁj������܂����B���ݒ��揤�ƍ��Z�̋��@�ł��B �r���T���[�̒������I����A�������������Ƙb����܂����B���A���^�����łP�X�X�X�N�̗��s�ŃX�g���[�g�`���h�����ɏo��A���̌����ɐ�����p�ɑł�������ƒm�肽���Ǝv���悤�ɂȂ�A�f���[�̃W�����n���l���[��w�ɗ��w���ꂽ�킯��b����܂����B����A��ʂ̕����킹�ĂS�R���̎Q�������萷��̂����ɏI���܂����B
�r���T���[�̒������I����A�������������Ƙb����܂����B���A���^�����łP�X�X�X�N�̗��s�ŃX�g���[�g�`���h�����ɏo��A���̌����ɐ�����p�ɑł�������ƒm�肽���Ǝv���悤�ɂȂ�A�f���[�̃W�����n���l���[��w�ɗ��w���ꂽ�킯��b����܂����B����A��ʂ̕����킹�ĂS�R���̎Q�������萷��̂����ɏI���܂����B