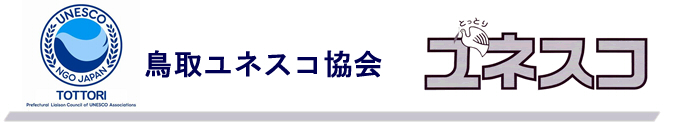
トップページ
鳥取ユネスコ協会とは
会長あいさつ
お知らせ
鳥取ユネスコ協会のあゆみ
こんな活動しています
日本ユネスコ協会連盟
研修会(談話会)
講演会
こども英語教室
絵手紙教室
国際交流
絵画展
文化の旅
チャリティーバザー
コーアクション
鳥取砂丘一斉清掃
会報の発行
ビッグニュース
いっしょに活動しませんか
※入会のご案内
会員名簿
正会員、賛助会員、法人会員
特別法人会員
|
|

|
鳥取ユネスコ協会 副会長 吉田茅穂子
現在の「日本丸」という船は、どこへ漂流していくのだろうか。現在の私たちの暮らしは先行き不透明で誰もが不安にかりたてられている。
そこで藤田安一先生にお話していただき、要約いたしました。
まず、経済は循環しており「好況」から最悪の「恐慌」を経て回復
過程の「不況」がある。景気が悪くても社会福祉、社会保障が充実し
ている国こそが先進国である。
かつて日本は中流層が多く安定していたが、今では下流層が増えて
犯罪も増し、社会が不安定になっている。
そして、貧困が増えている原因の一つは、不安定な雇用と労働条件
の悪化であり、二つ目は財政の所得再配分機能の弱体化である。日本
の税制は大企業や金持ちを優遇する仕組みになっている。
三つ目は、教育費負担の増大であり、日本では教育費は自己負担が当然であり社会的支援が乏しい。このため下流層の子どもは進学の機会を持つことが難しい。
さらに国際的要因として、円高やヨーロッパ経済混乱などが日本の経済を悪くしている。
このため日本は、海外の影響を受けやすい。外需依存型から内需拡大経済に転換するしか道はない。そのために安定した雇用環境を作り出し国民の購買力を高める必要があり、外需と内需を両輪としてバランスの良い経済発展をしていかなければならない。
以上のような先生の貴重なお話を聞き、一日も早くこの困難な時期を
脱し、少しでも豊かな国になっていくよう行政と国民が一体となり努力
していくべきと切実に感じたところです。
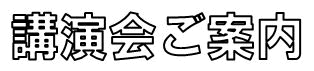
日本経済を、いかに再生するか!
わたしたちの暮らしはどうなるの?

講師:鳥取大学地域学部教授●経済学博士
藤田 安一 先生
藤田 安一 先生
とき : 2012/6/3(日) PM2:00より 入場無料
ところ : さざんか会館 2階市民活動センター/鳥取市富安2-104-2
詳しくは・・・ PDFファイルでご覧頂けます。 ご案内(1,454KB)
2011年5月15日(日)
場所/鳥取県立図書館 大研修室
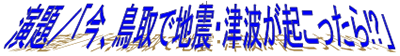
〜安全を守るには〜
講師/鳥取大学名誉教授・放送大学鳥取学習センター所長
西田 良平 先生

「講演を聞いて」
鳥取ユネスコ協会・副会長 吉田茅穂子
鳥取ユネスコ協会・副会長 吉田茅穂子
2011年3月11日の東日本大震災の直後でもあり、市民の関心も高く、約250名のお客様をお迎えし、会場はあふれんばかりであった。
先生のお話は、まず巨大津波のシミユレーションを見ながら、地震直後の津波警報が出されたらすぐに高い場所へ避難することがもっとも大切であると、そしてこのたびの大地震は海底断層の変動により長さ450km、幅200kmにわたり海面が盛り上がって起こったという。
想定外の巨大地震といわれるが、100年に5〜6回もこの地球上に巨大地震が起こっており、決して「想定外」ではないこと。日本海の地震津波は、秋田県・青森県沖でほとんどが太平洋側に震度5強の地震津波が予想されており、東海沖、東南海沖では、約60〜80パーセントの確立で起るといわれている。
鳥取県を考えると、山崎断層があり、マグニチュード7の地震が起こると何回も余震が続くだろう。そして、もし、東南海地震が起こったら、鳥取県はマグニチュード5弱が想定され、特に積雪時には更に被害が拡大し複合被害が起こると考えられる。そして最後に、「自助」「共助」「公助」が必要であるとおっしゃられた。
このたび、西田先生の御講演をお聞きし、いざという時にいかに日頃の心構えと知識が必要であるかということを改めて再認識した。
終わりに、ご多忙でいらっしゃる西田先生に、このような切実なお話を専門的な立場から、分かりやすく詳しくお話していただきユネスコ会員は勿論のこと一同心より感謝申し上げます。
All Rights Reserved Tottori UNESCO Associations.
鳥取ユネスコ協会
鳥取ユネスコ協会
 まず三徳山はその昔神と仏の宿る霊山として知られ、多くの人々の信仰を集め、そして三徳山の開山は慶雲三年(七〇六)と言われており、その縁起は役行者の「蓮の花びらの伝説」として今に伝えられているということです。
まず三徳山はその昔神と仏の宿る霊山として知られ、多くの人々の信仰を集め、そして三徳山の開山は慶雲三年(七〇六)と言われており、その縁起は役行者の「蓮の花びらの伝説」として今に伝えられているということです。 先生は、まず自然を「見る」「看る」「観る」ことから始めなければならないと。そして教育者であられる立場から、子どもたちが自然の中に入り、触れ、成長していくべきである。そして、まさに日本の童謡唱歌は、日本の教育の原点を訴えていること。たとえば、「春の小川」「ほたる」「すずめの学校」「めだかの学校」などの歌詞にすべて教訓がこめられていると話された。
先生は、まず自然を「見る」「看る」「観る」ことから始めなければならないと。そして教育者であられる立場から、子どもたちが自然の中に入り、触れ、成長していくべきである。そして、まさに日本の童謡唱歌は、日本の教育の原点を訴えていること。たとえば、「春の小川」「ほたる」「すずめの学校」「めだかの学校」などの歌詞にすべて教訓がこめられていると話された。