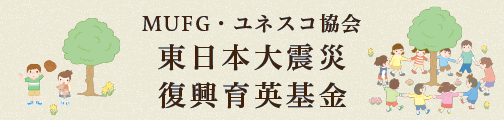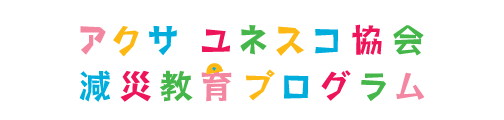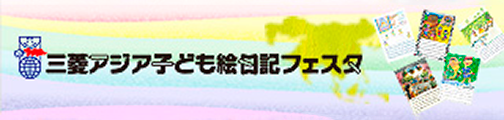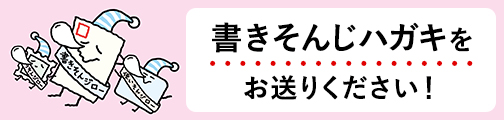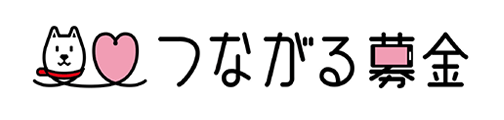未来遺産運動ニュース増刊号~学校との連携を通じて地域の伝統文化を継承~
日本各地で継承されてきた祭礼や行事において、地域の人たちが演じる歌や舞、踊り等の民俗芸能は、少子高齢化、過疎化等の影響により、次世代への継承が喫緊の課題となっています。
このような社会背景のもと、「プロジェクト未来遺産」に登録された多くの活動では、創意工夫をはかりながら次世代への継承が進められています。
今号では、地域の学校と積極的に連携をはかり、後継者の育成や地域コミュニティへの普及活動を進めている香川町農村歌舞伎保存会※(2010年「プロジェクト未来遺産」に登録)相談役の鎌田さんより、子どもたちへ伝承していくための工夫や課題を教えていただきました。
地元小中学校との連携のきっかけ
①中学校:昭和57年、郷土芸能部の15名の生徒の研究活動を契機に
娯楽の変化により、昭和50年代に衰退の危機を迎えました。風前の灯火であった祇園座は、地元の県立香川第一中学校の郷土研究部生徒による研究活動がきっかけとなり、昭和57年に再興しました。
熱心な中学生の研究活動のおかげで、大人たちにも指導の熱が入り、中学生だけで本能寺夜討の場を演じることができました。それ以来、コロナ禍を除き、現在も11名の部員に週2回稽古を行い、文化祭や地域のお祭り等での上演が続いています。

②小学校:学習指導要領の改訂を受けて平成21年から連携開始
祇園座の指導のもとで行われる「白浪五人男」の素人公演活動に、高松市立川東小学校の校長が含まれていたこともきっかけとなり、川東小学校との連携が開始しました。
5年生の総合学習の時間では、20~30人の生徒を対象に、5月~11月まで週2回の稽古を行い、文化祭などにて年3回の「白浪五人男」の公演を行っています。
4年生の年2回の校外学習では、東谷地区の竹炭体験や芋掘りなど、複数の体験プログラムのうちの一つに農村歌舞伎体験も取り入れられました。これまでは生徒が複数から選択していましたが、今年からは生徒37名の4年生全員が歌舞伎体験を行うことが決定しました。

子どもたち、先生と顔の見える関係づくり
子どもたちに関心を持ってもらうために、子どもたち一人ひとりの個性を生かして、その子にあった形で教えるようにしています。子どもたちは敏感で、中途半端な知識や技術は通用しません。子どもたちから教えられ、気づかされることも多く、子どもたちが先生です。指導する大人を「先生」とは呼ばせず、学びあうというスタンスで取り組んでいます。

また、学校との連携を継続するための工夫として、最近は先生が多忙で、地域の人と交流する機会が少ないように感じています。そのため、週一回先生の代わりに見守り活動を行ったり、年1-2回の学校の環境美化活動への参加等、顔の見える関係構築を意識しています。
学校を核として広がる地域の伝統文化
現在保存会の会員25名ですが、10代~70代後半と幅広く、中学生、高校生も会員として活動を支えてくれています。高校、大学、大人になってからも保存会に協力してくれたり、その親御さんも会員になって活動する人も出てきています。

学校を核として歌舞伎の伝承を推進することは、郷土愛の醸成はもちろん、地域イベントを通じて世代間交流も生まれます。子どもたちの公演には、親御さんやおじいちゃん、おばあちゃんも見に来てくれます。地域が一体となって伝統文化を盛り上げ、伝承していくためには、「子どもの持つ力」がとても大事だと考えています。
※農村歌舞伎祇園座とは
農村歌舞伎祇園座は、香川県高松市香川町の東谷地区で180年以上伝承されてきました。江戸時代後期に阿波(徳島)へ出稼ぎに行った香川町東谷地区の若者たちが習得した芝居が始まりと言われています。
庶民の娯楽として親しまれてきた祇園座は、座長や小屋(平成13年に建設)を持たず、荷車を押して各地を回り、公演を行っていました。太三味線・下座音楽・床山・舞台方・衣裳方等、全てを自ら受け持ち、自ら芝居(演技・演出)もするというのが特徴です。
未来遺産運動では、多くの方々に身近な地域や全国各地の「プロジェクト未来遺産」に関心を持っていただくことで、地域を超えた新たなつながりを生み出し、全国に応援の輪が広がることを目指しています。